
(一社)宅建協会千葉支部の事業及び事務連絡を発信します。コメント等書き込みは受け付けておりませんのでご了承ください。
2024/10/31| 調査研究センター
宅建協会千葉支部の調査研究センターでは、賃貸・売買窓口担当者向けの研修会を開催いたします。
研修内容は、次のとおりです。
1.クロネコ 高齢者の見守りサービスについて
(講師:ヤマト運輸)
2.宅建業に関わる直近の法改正と実務上の疑問点について
(講師:千葉支部顧問弁護士 安川秀穂)
3.重要事項説明とグレーゾーン解消対策
(講師:(有)エスクローツムラ 津村重行)

(画像は過去の研修会の様子です)
日 時 令和6年11月8日(金)
午後1時より午後4時30分まで
*受付12時30分
場 所 千葉県宅建会館(県本部)
千葉市中央区中央港1-17-3
単 位 180単位
定 員 先着200名 専用申し込み書にて受付します
申込締切り 10月31日(木)
申 込 先 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 千葉支部事務局
TEL 043-242-0175 FAX 043-242-0176
宅建協会千葉支部では、千葉市に協力し、
空き家の活用相談・現地調査員を派遣しております。
詳細はすまいのコンシェルジュ へ
2009/10/30| 調査研究センター
----日管協メールマガジン(会員専用版)から----
10月29日、更新料を有効とする大阪高裁の判決がありました。
これは、更新料支払い特約(2年ごとに2か月分)を巡って今年3月27日、大津地裁で貸主側が勝訴した(借主側の請求が棄却された)事案の控訴審です。
<経緯>
原告(借主)は平成12年8月、賃料5万2千円、更新料2か月等の条件で滋賀県の物件に入居。2年ごとに2か月分の更新料を2回、3回目の更新時は1か月分を支払った。
退去後、原告は「更新料支払いの約定が消費者契約法10条または民法90条に反して無効である」と主張して、5か月分の更新料26万円の返還等を求めたが、21年3月27日、大津地裁はこれを棄却。
原告はこれを不服として3月31日に控訴。大阪高裁は本日、これを棄却した。
<大阪高裁の判決の内容等>
詳細が分かりましたら、後日、改めてお知らせいたします。
<参考:大津地裁の判決全文>
(賃貸マンション更新料問題を考える会のページより)
http://www.koushinryou.net/document/otsukoushin.pdf
<参考:大津地裁の判決の要点>
(以下、3月27日の日管協メルマガより)
<賃貸借契約書の記載>
第2条(契約期間・更新)
標記の契約期間満了の1ヶ月前までに、甲、乙のいずれからも書面による異議申出のない場合は更に2年間更新されるものとし、以後も同様とする。その場合、乙は甲に対して契約更新料として標記の通り支払うとともに、更新に必要な書類を甲に提出するものとする。
<更新料の法的性質に関する裁判所の判断>
1.賃料の補充(一部前払い)の性質
・賃貸借契約書および重要事項説明書、また本件建物の広告に家賃や更新料の記載がある。
・証拠によれば京滋地区においては更新料の慣行が長年にわたり存続し、17年4月からの1年間に契約された物件に限っても、55.1パーセントの契約に更新料(平均1.4か月)の定めが設けられている。
・「借賃以外に授受される金銭の額及び当該金員の授受の目的」は重要事項説明の対象であるから、仲介業者は更新料(更新時に授受され、返還されない)について説明したと推認される。
・よって、原告は賃料や礼金、更新料を支払う必要があると認識し、立地、間取り、設備等とあわせて複数の賃貸物件と比較した上で、自らの需要に最も合致した物件を選択したと推認される。
・貸主が更新料名目の一時金を設ける趣旨は、月額賃料等のみならず一時金をも加えて目的物の使用収益の対価として把握し、契約期間終了時までに受領すべき賃料の一部を前払いにより回収する代わりに、その分月額賃料を低くするというところにあると推認される。
・つまり貸主・借主とも一時金が設けられているとの認識は合致しており、本件更新料は、合意更新後の賃料の一部前払いとしての性質を有するものというべきである。
2.更新拒絶権放棄の対価の性質
・更新料を、更新拒絶の放棄の対価とみることは可能。とはいえ更新拒絶の正当事由が認められることは経験則上多くはないから、更新拒絶権放棄の対価たる性質は希薄といえる。
3.賃借権強化の機能
・契約途中で貸主が解約を申し入れないという意味で更新料に賃借権強化の機能が認められる。とはいえ貸主の正当事由が認められることは経験則上多くはないから、賃借権強化の対価たる性質は希薄といえる。
4.結論
・更新料支払い条項は、目的物の使用収益の対価たる賃料の一部前払いおよびその額を定めた条項である。
<消費者契約法との関係についての裁判所の判断>
1.法10条前段の要件(民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の義務を加重する消費者契約の条項)に該当するか・更新料支払い条項は、更新後賃料の一部を前払いさせる
ものであり、賃料の後払いを定めている民法614条と比べて、借主の義務を加重している。
・また、借主により中途解約されたときにも返還・精算されず、使用収益が無いのに対価だけ徴収されることから、民法上の任意規定が適用される場合と比較して借主の義務を加重するものであるといえる。
・よって、更新料支払い条項は、消費者の義務を加重している。
2.法10条後段の要件(民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの)に該当するか
・更新料支払い条項は、借主が負担すべき額や次期が明確であり、判断の前提となる情報は開示されていたうえ、京滋地区で長年普及した概念である。
・証拠によれば、民間賃貸住宅のストック数は量的に充足しており、原告が更新料条項を不当と考えた場合には他の賃貸物件を選択することが容易だった。原告は自由意思で本件物件を選択しており、貸主が情報力・交渉力の格差につけ込み、自己に一方的に有利な契約条項を借主に押し付けたとはいえない。
・よって、更新料支払い約定に、消費者の利益を一方的に害する事実は認められない。法10条後段の要件に該当し無効であるということはできない。
<判決>
以上の次第で、原告の請求は理由がないからこれを棄却する。
2009/10/23| 調査研究センター
第1回 調査研究センター 政策問題研究会
平成21年10月22日(木)16時00分~
場所:宅建千葉支部会館 2F 大会議室
議題「中小企業向け政府金融政策等について 」
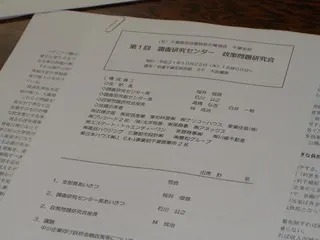
会員23名が会議に参加。

中小零細企業向け金融対策について、メリット、デメリット、問題点。平成10年の頃の倒産は何故起こったか? モナトリウム法案はいつ発動すれば良かったか。等々についてディスカッションしました。

会議内容は後日、政策問題研究会(調査研究センター長:石川公之、座長:林成治)にて精査し、お知らせする予定です。
2009/10/9| 調査研究センター

10月8日(木)午後1時から、千葉県不動産会館にて
賃貸売買窓口担当者研修会が行われました。
石川調査研究センター長 ごあいさつ

講師 日管協総合研究所 研究員 本田 勝祥様

講習内容
1.(財)日管協版「賃貸住宅トラブル対処法改訂版」の解説
講師 本田 勝祥(日管協総合研究所 研究員)
2.重要事項調査の範囲と物件調査ノウハウ
講師 津村 重行(不動産コンサルタント)
3.賃貸をとりまく諸問題
共同住宅の地上波デジタル、光ケーブル他
講師 川辺 博行 他
不動産コンサルタント 津村 重行 様 
お申し込みは200名定員に対して250名ありました机の数に限りがあることをご了解いただうえで受付させていただきました。
ですが昨日は台風18号に襲われ、受付時間の頃には、JR総武線・京葉線、一時はモノレールまでも動かなくなるなどの最悪のコンディションの中、約200名の方にご参加いただきました。
「管理しているアパートの看板が飛ばされて、それを直してから一生懸命走ってきました。それでも、聞きたい、参加したい研修会」という声もありました。
千葉支部: 参加社数133社 参加人数164名
他支部: 参加社数16社 参加人数16名
2009/10/5| 調査研究センター
平成21年度 賃貸売買窓口担当者向け研修会受付終了
200名を定員とさせていただきましたが、お申し込みが殺到し、「机がなくてもよければ」とご了解をいただき、資料の取り寄せ可能な限り受け付けさせていただきました。
誠に申し訳ございませんが、これ以上の受付は致しかねますので、ご容赦ください。 (10月5日 調査研究センター長)
当日は、受講生の受付をし、席にご案内させていただきます。
内容
1.(財)日管協版「賃貸住宅トラブル対処法改訂版」の解説
講師 本田 勝祥(日管協総合研究所 研究員)
2.重要事項調査の範囲と物件調査ノウハウ
講師 津村 重行(不動産コンサルタント)
3.賃貸をとりまく諸問題
共同住宅の地上波デジタル、光ケーブル他
講師 川辺 博行 他
日 時 平成21年10月8日(木)受付12時30分
開 催 午後1時より午後4時30分まで
場 所 千葉県不動産会館 3F(中央区中央港1-17-3)
定 員 先着200名 申込締切 9月25日
単 位 4単位
※ 駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。
2009/9/17| 調査研究センター
平成21年度 賃貸売買窓口担当者向け研修会開催
内容
1.(財)日管協版「賃貸住宅トラブル対処法改訂版」の解説
講師 本田 勝祥(日管協総合研究所 研究員)
2.重要事項調査の範囲と物件調査ノウハウ
講師 津村 重行(不動産コンサルタント)
3.賃貸をとりまく諸問題
共同住宅の地上波デジタル、光ケーブル他
講師 川辺 博行 他
日 時 平成21年10月8日(木)受付12時30分
開 催 午後1時より午後4時30分まで
場 所 千葉県不動産会館 3F(中央区中央港1-17-3)
定 員 先着200名 申込締切 9月25日
単 位 4単位
締め切りは9月25日ですが、申し込み者は現在190名ほどになりました。 お早めにお申し込みください!
※ 駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。
2009/9/3| 調査研究センター
昨日の大阪高裁の更新料訴訟ですが、判決文(全文)が更新料問題を考える会のホームページに掲載されましたので、お知らせいたします。
判決文(PDFデータ、全53ページ)はこちら
2009/9/2| 調査研究センター
平成21年度 賃貸売買窓口担当者向け研修会開催
内容
1.(財)日管協版「賃貸住宅トラブル対処法改訂版」の解説
講師 本田 勝祥(日管協総合研究所 研究員)
2.重要事項調査の範囲と物件調査ノウハウ
講師 津村 重行(不動産コンサルタント)
3.賃貸をとりまく諸問題
共同住宅の地上波デジタル、光ケーブル他
講師 川辺 博行 他
日 時 平成21年10月8日(木)受付12時30分
開 催 午後1時より午後4時30分まで
場 所 千葉県不動産会館 3F(中央区中央港1-17-3)
定 員 先着200名 申込締切 9月25日
単 位 4単位
※ 駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。
9月7日付けにて、会員の皆様にハガキでご案内します。
2009/7/28| 調査研究センター
以下は財団法人日本賃貸住宅管理協会が発行するメールマガジンから引用させていただきました。
ニュースやインターネット等で大きく採り上げられていますので皆様ご存知と思いますが、昨日、「消費者契約法により更新料は無効」との判決が京都地裁でありました。
取り急ぎ、この判決をどのように受け止めたらよいかについて、以下、事情に詳しい方のコメントを紹介します。
<A氏コメント>
地裁レベルでは更新料を認める判決が繰り返されていましたが、今回は認めない判決があった。それだけのことです。
同じような訴訟でも主張の仕方で判決は異なりますし、同種の主張がなされても同じ裁判所で異なる判決が出ます。司法は案件を個別に判断します。原状回復の訴訟などは良い例でしょう。
「貸主が勝ったから今後は通常損耗負担特約は有効だ」とか「借主が勝ったからもう特約は無効だ」などと、皆様は考えていないはずです。
更新料訴訟の判例は、まだ確立されているとはいえない状況にあります。
更新料の今後の流れを左右する判決として注目すべきは、今年8月27日に大阪高裁の判決が予定されている訴訟です(昨年1月30日、京都地裁では貸主が勝訴)。
この大阪高裁の訴訟は貸主側・借主側とも弁護団を組織し、裁判官の求めに応じて双方が著名な学者等の意見書を提出していますので、多くの論点について考察した判決が出るでしょう。
最終的には最高裁まで争われるとも言われており、8月27日を以て更新料の判例が確立されることにはならないかもしれませんが、当面の流れを大きく左右するのはこの判決といえるでしょう。
<参考:以下、昨年1月30日のメールマガジン>---
京都地裁で争われていた更新料の是非をめぐる訴訟は本日、貸主側が勝訴しました(借主側の請求は棄却)。
以下に判決要旨を紹介します。
(なお、借主側は控訴する考えのようです)
<概要、昨年10月12日のメールマガジンより>
賃貸借契約の更新時に更新料を課すのは消費者契約法に違反するとして、京都市の男性が貸主に更新料等61万5千円の返還を求めた訴訟(4月13日)は、簡易裁判所から地方裁判所に移管された。
この男性は賃料4万5千円で平成12年8月に賃貸借契約を締結して京都市のマンションに入居。契約書の約定に従って毎年10万円の更新料を支払っていたが、部屋ごとに更新料の金額が違うことを知って18年に更新料の支払いを拒否。
京都の弁護士会が開設した「更新料110番」に相談をして、今回の訴訟に至ったとのこと。
<判決要旨>
第1 結論・・・請求棄却
第2 事案の概要
被告との間で賃貸借契約を締結し、被告の所有する物件 に居住していた原告が、更新料支払いの約定が消費者契約法10条又は民法90条に反して無効であると主張して、既払いの更新料の返還等を求めた事案
第3 判決理由の要旨
1 更新料の法的性質について
(1)更新拒絶権放棄の対価(紛争解決金)・賃借権強化の対価の性質について
ア 更新料が授受され合意更新が行われる場合、賃貸人は、更新拒絶の通知をしないで、契約を更新するのであるから、更新料は、更新拒絶権放棄の対価の性質を有する。
また、法定更新の場合(更新後は、期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人からいつでも解約申し入れが可能となる。)とは異なり、合意更新により更新後も期間の定めのある賃貸借となる場合には、賃借人は、期間満了まで明渡しを求められることがない上、賃貸人が将来、更新を拒絶した場合の正当事由の存否の判断にあたり、従前の更新料の授受が考慮されるものと考えられるから、更新料は、賃借権強化の性質を有する。
イ もっとも、常に更新拒絶や解約申入れの正当事由があると認められるものではなく、特に、本件のように専ら賃貸目的で建築された居住用物件の賃貸借契約においては、正当事由が認められる場合は多くはないと考えられるし、本件賃貸借契約の期間は1年間と比較的短期間であり賃借権が強化される程度は限られたものであるから、本件更新料の有する、更新拒絶権放棄の対価・賃借権強化の対価と しての性質は希薄である。
(2)賃料の補充の性質について
ア 上記のとおり、本件更新料の有する、更新拒絶権放棄の対価及び賃借権強化の対価として性質は希薄であるにもかかわらず、原告と被告は、更新料支払の約定のある本件賃貸借契約を締結している。
このような契約当事者の意思を合理的に解釈すると、賃貸人は、1年目は、礼金と家賃を加算した金額の売り上げを、2年目以降は、更新料と家賃を加算した金額の売り上げを期待しているものと考えられ、他方、賃借人は、更新料を含む経済的な出損を比較検討した上で、物件を選択しているとみることができる。そして、原告又は被告が、これと異なる意思を有していたことを認めるに足りる証拠はない。
イ このように、本件更新料は、本件物件の賃貸借に伴い約束された経済的な出損であり、本件約定は、1年間の賃料の一部を更新時に支払うこと(いわば賃料の前払い)を取り決めたものであるというべきである。
2 本件約定が民法90条により無効といえるか
本件更新料は、その金額、契約期間や月払いの賃料の金額に照らし、直ちに相当性を欠くとまではいえないから、本件約定が民法90条により無効であるということはできない。
3 本件約定が、消費者契約法10条により無効といえるか
(1)消費者契約法10条前段の要件(「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の義務を加重する消費者契約の条項」)を満たすか。
本件更新料が、主として賃料の補充(賃料の前払い)としての性質を有していることからすると、本件約定は、「賃料は、建物については毎月末に支払わなければならない」と定める民法614条本文と比べ、賃借人の義務を加重しているものと考えられるから、本件約定は、上記要件を満たす。
(2)消費者契約法10条後段の要件(「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」)を満たすか。
・本件更新料の金額は、契約期間や賃料の月額に照らし、過大なものではないこと
・本件更新料約定の内容は明確である上、その存在及び更新料の金額について原告は説明を受けていることからすると、本件約定が原告に不測の損害、不利益をもたらすものではないこと等を併せ考慮すると、本件約定が上記要件を満たすもの とはいえない。
(3)結論
以上より、本件約定が消費者契約法10条により無効であるということはできない。
以上
<参考>-----
・民法90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
・更新料問題を考える会のホームページはこちら
(アクセスが集中し、つながりにくくなっているようです)
http://www.koushinryou.net/
==========================
以上、財団法人日本賃貸住宅管理協会が発行するメールマガジン(会員専用)から、参考にさせていただきました。